【ひな祭りの由来とは?】簡単手作り!サステナブルチョークの作り方も

意外と知らない「ひな祭り」の由来
今年もだいぶ暖かくなってきましたね。
梅も咲き、春の訪れを感じ始めている方も多いと思います。
さて早速ですが、お雛様ってどうして飾るのか、皆さま理由はご存知ですか?
お雛様には、女の子の穢れを移し、厄災の身代わりになってもらうという意味が込められています。
由来は諸説あるようですが、有力なのは中国でおこなわれていた「上巳(じょうし/じょうみ)の節句」が日本に伝わってきたという説です。
上巳(じょうし/じょうみ)の節句とは?
もともとは邪気や厄を払うための行事で、人形に自分の邪気を移して川に流すという「流し雛」がおこなわれていたそうです。それが時代とともに、流し雛に使用する人形が立派になり、川に流すのではなく家に飾るようになったようです。
これがやがて“ひな人形”と呼ばれ、貴族の中で流行っていたおままごと遊びのような“ひな遊び”と合わさって、「ひな祭り」になったといわれています。
そして、江戸時代に幕府が五節句を定めるのですが、その時に「人形は女性のもの」ということで、3月3日はひな祭りという女性の行事になりました。初節句を華やかに祝う習慣と相まって、庶民にも広まったのだそうです。
ひな祭りは子どもの行事というイメージが強いですが、もともとは「女性の幸せを願う日」、さらにその前は老若男女問わず「厄払いの日」だったということですね。
ひな祭りにやることと言えば?

ひな祭りだ!といっても、これまでなにをして過ごしてきたでしょうか?
今回は、ひな祭りの過ごし方のアイディアを簡単にいくつかご紹介します。
<ひな祭りの過ごし方>
・梅の花を見に行く
・着物を着て出かける
・家族写真を撮る
・ちらし寿司を食べる
一般的には、親族で集まってお祝い(宴会)をすることが多いようです。小さな女の子がいるご家庭なら、着物を着て素敵な写真を撮ることも思い出になっていいですね。
また、昔は「女性の幸せを願う日」であったとのことなので、固定概念を振り払って、日ごろの感謝の思いを男性から女性に伝えたら喜ばれるかもしれませんね…♪
簡単サステナブル!卵の殻で手作りチョークも
最後に、ひな祭りにできるサステナブルを少しご紹介します。
「面白そう!」と思った方は、ぜひ実践してみてください。
先ほど挙げたように、ひな祭りのごちそうといえば「ちらし寿司」ですよね。
そんなちらし寿司には錦糸卵を最後に散らすかと思います。
そこで出る、“卵の殻(カラ)”―実はこれ、色んなことに再利用できるんです。
今回は、その再利用方法をいくつかピックアップします。

1.土にまいて肥料にする
卵の殻にはカルシウムがたっぷり含まれているので、とても良い肥料になります。
家庭菜園などやっている方にはとてもオススメです。
ただ、実際に吸収されるまでには時間がかかるようなので、なるべく細かく砕いてからまくことがポイントです!
2.チョークを作る
卵の殻と小麦粉と水だけでカンタンにチョークを作ることができます。
子どもと一緒につくってみても楽しいと思います!
作り方はザックリ以下のような流れになります。
①殻の内側の膜(卵殻膜)を取って粉状になるまで砕く
(フードプロセッサーで攪拌して、すり鉢などですると早いです)
②小麦粉と水を混ぜ合わせる
(卵3~4個に対して小麦粉:小さじ1杯、水:小さじ1杯半くらい)
→色つきのチョークにしたい場合は、水:小さじ1杯、食料色素:小さじ1杯にしましょう!
③混ぜ合わせたものを好きな形にして乾燥させる
(しっかり乾燥させるため、数日間は置きましょう)
3.洋服の汚れを落とす
やり方はこれまたカンタンです。
お湯を沸かした鍋に、砕いた卵の殻とよごれを落としたい衣類を入れて30~40分煮るだけ!
よごれが落ちるのは、卵の殻に含まれる炭酸カルシウムが理由です。
殻を加熱すると酸化カルシウムとなり、それが二酸化炭素と反応してお湯をアルカリ性に変えるそうです。科学の授業みたいですね。
----🎎――――🎎――――🎎――――
以上、卵の殻の活用方法の一例でした。
調べてみると、ほかにもさまざまな活用方法があるようです。
今年はひな祭りのあともいつもと違う楽しみ方をしてみてはいかがでしょう?
気になった方はぜひ試してみてください。
皆様も楽しいひな祭りをお過ごしください。
☞ひな祭りのあとはホワイトデー!
☞お財布にも健康にもいい?「ゼロウェイスト」な暮らし
 ご相談・お問い合わせ
ご相談・お問い合わせ
ご相談希望の内容を下記より選択ください。(複数選択可)


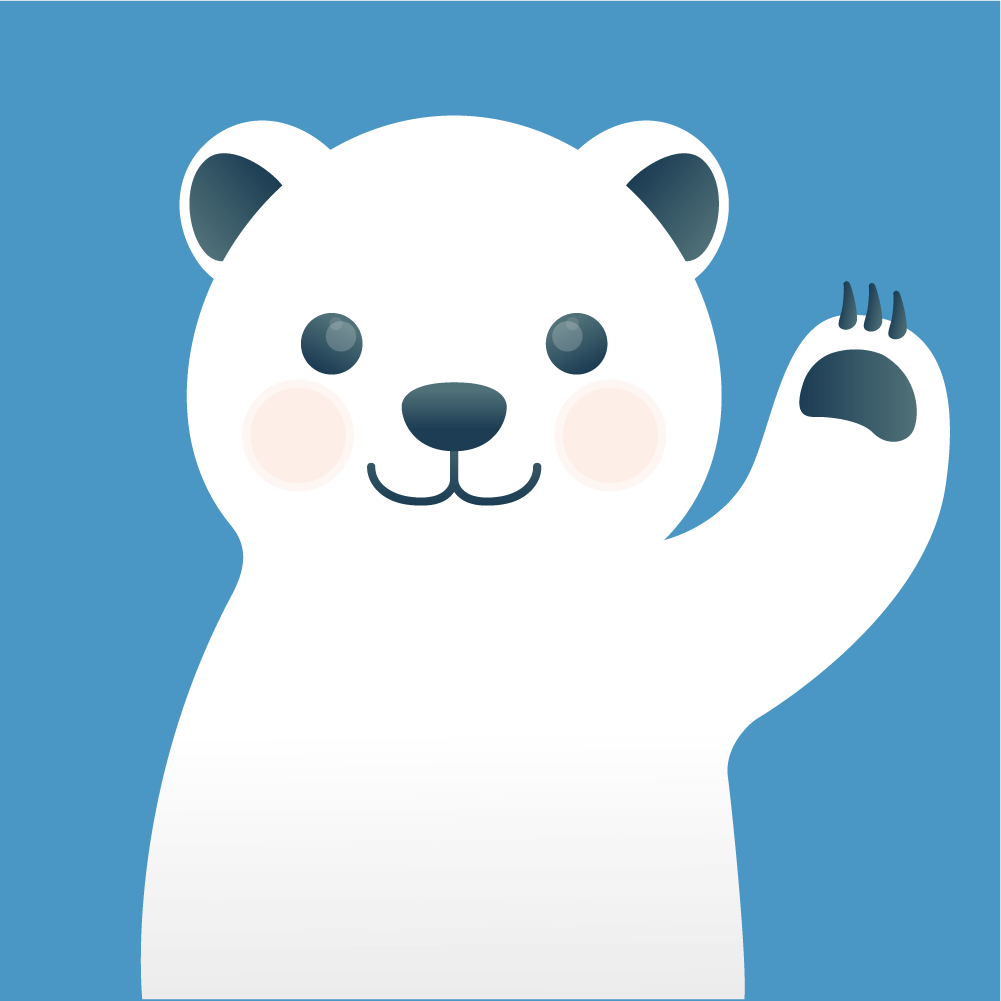


![環境にやさしい自然派シャンプー3選[メンズにもおすすめ!]](https://sustainable-switch.jp/wp-content/uploads/2022/06/サステナブルシャンプー3選-800x533.jpg)
![エシカルとは?[意味と具体的なエシカル商品・グッズをご紹介]](https://sustainable-switch.jp/wp-content/uploads/2021/11/マスキングテープ-rotated-e1670311188794-800x512.jpg)